2025-05-07
人とAIの関係性を設計しよう Embedding / Copilot / Agent の三類型
自分が作るプロダクトの中で、人間とAIはどのような関係性を築くのか?
壮大なテーマに聞こえるかもしれないが、実はプロダクト開発における実務的な問いだと思っている。もう少し現場的にいえば、「人間に対して、AIをどのような位置に立たせて仕事をさせるか」ともいえるかもしれない。ユーザー体験やプロダクトの意味合いは、この設計次第で大きく変わってくる。
この問いに向き合うためのフレームとして、僕が最近出会って腑に落ちたものを紹介したい。中国のあるデザイン系メディアで紹介されていた「人間とAIの協働における三類型」という整理だ。以下の図は、そこで紹介されていたものを僕が翻訳し、わかりやすくするために少しだけ改変したものである。

この図では、人とAIが協働する際の関係性をEmbedding(裏方)、Copilot(共同作業者)、Agent(代理人)という三つの型で捉えている。タスクの進行プロセスを縦に示し、それぞれの協働スタイルを横に並べた形だ。
Embedding(裏方):AIが部分的に人間のタスクを補助するモード
作業の大部分はユーザーが主導し、AIはその中の一部の工程、情報検索や判断材料の提示といった領域で、さりげなく手を貸す。ゴールの設計や意思決定、最終的な実行はあくまでユーザーが担っており、AIはタスクの断片にだけ「埋め込まれて」いる。たとえば、フォームの自動補完、スマートな並び替えの提案、画像の自動補正、検索時のキーワード補強などがその例だ。大抵の場合、ユーザーはAIを「操作している」という感覚すら持たないことも多く、なんとなく便利、くらいの感覚で使われている。
Copilot(共同作業者):AIが人間と並走し、随時サポートや提案を行うモード
作業の主導権はユーザーが持ちつつ、AIはその過程で「一緒に考える相手」として振る舞う。タスクの中で特定の処理を代わりに行うこともあるが、その成果物はユーザーの確認・修正を経て進められる。GitHub CopilotやNotion AIのように、ユーザーが言語化した意図を受け取り、それに応じたアシストをしてくれる例がこれにあたる。
Agent(代理人):ユーザーが目的を設定したあと、AIがその達成に向けてタスクを分解し、適切なリソースや手段を選びながら自律的に進めていくモード
ユーザーは起点のアクションと最終確認を担うが、途中の過程ではAIが代理人として意思決定し、進行する。AutoGPTのようなツールがこの例にあたり、ユーザーは「何をしたいか」を伝えるだけで、AIがステップを設計し実行していく。頼もしいけれど、ちょっと怖いと感じる人もいるかもしれない。SF映画ではだいたい人類を滅ぼしにかかってくる。
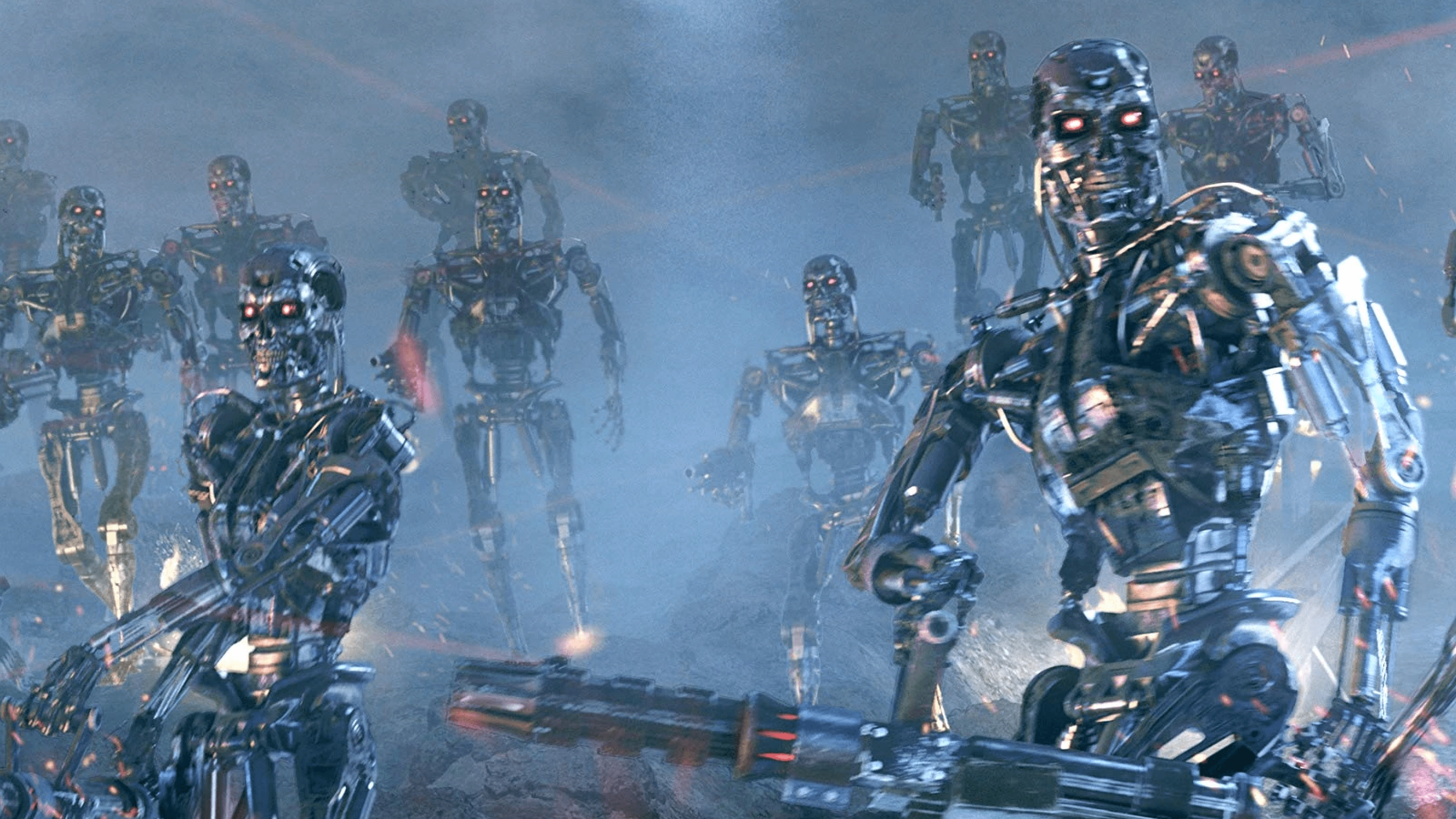
この三類型の整理がよいのは、AIの能力の高さや技術的な洗練度ではなく、「協働の構造」にフォーカスしているところだ。僕は、プロダクトの本質はこの協働の構造にあって、AI自体の技術力はその上に乗っかってくるパワーのようなものだと思っている。パワーでの戦いは、資本力の高いところに勝つのは難しい。しかし協働の構造を工夫するところには、ベンチャーにも戦える余地があると思う。
プロダクトにAI機能を実装するときには、この図を参考にして、ユーザーとAIの間にどんな関係性を築いていくのかを十分に議論するようにしていきたい。この図は、その議論をふわふわとした抽象論に留めず、図面的設計的に捉えてチームで共有するための叩き台になるはずだ。
そうした議論の延長として「関係性のフェーズ移行を設計する」ということも考えられるだろう。新しい機能は最初Copilot型でユーザーと一緒に試行錯誤しながら信頼を得ていき、一定の慣れが生まれたタイミングでAgent的な動きを提案していく、というような段階的な設計の可能性だ。協働のあり方を、固定された型ではなく、関係性の成熟に応じてシフトするものとして捉えてみると、より実用的な設計ができる気がする。
また、「関係性を構築する」というのは、「継続的な視点を持つ」ということでもある。人間同士がそうであるように、関係性はある程度の時間の中で育っていくものだからだ。実際の関係構築というのは、ドラマの脚本のように設定を与えれば完了するわけではない。このことは、自分の身の回りの関係が、「最初の印象」なんかよりも「どう付き合い続けてきたか」の方が強く影響していることからも分かるだろう。特に、ある関係のあり方を意図的に目指すのであれば、より計画的な取り組みと、適時の調整作業が必要だ。
関係性は持続され、反復されることによってのみ成立する。「関係性」とは一定の距離感と進入角度のことを指すのではなく、二者の接触によってその都度、距離感と進入角度が共創的に試行錯誤し続けられる「状態」のことを指すのだ。
(宇野常寛、2022『砂漠と異人たち』朝日新聞出版)
美涼は、それはそんなに難しくないという顔で、 「わかったってところから、また愛し直すんじゃないですか? 一回、愛したら終わりじゃなくて、長い時間の間に、何度も愛し直すでしょう? 色んなことが起きるから。」と言った。
(平野啓一郎、2018『ある男』文藝春秋)
まだまだAI機能のデザインは始まったばかりなので、これからいろいろとAI搭載のプロダクトを作っていけば、より詳細な類型化もできるかもしれない。もとより人と他者の関係のあり方は一様ではないし、型通りのもので終わる話でもないだろう。AI機能を観察するときに「この機能は、人とAIをどのように協働させるものなのか」という問いを持つことで、僕たちはより実務的なデザイナーの目を養うことができると思う。
どうすればAIとの関係が、日々の営みに溶け込んで、自然にそこにあるものとして続いていくのか。使えば使うほど馴染んでいくような関係性は、どうしたら作ることができるのか。そんなことを話し合って設計された機能こそが、ユーザーに利便性以上のものをもたらし、プロダクトの価値を高めていくはずだ。

